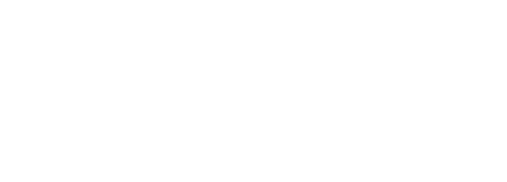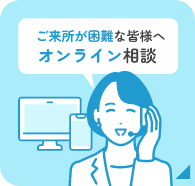事業用財産
給与所得者であれば収入源と形成財産は明確に区別できます。しかし、自営業者、特に個人事業主においては、収入を生み出す事業用財産と生み出された収入によって形成された財産が混在していることがあります。そのため、離婚時にどこまでの財産が財産分与において対象となる財産なのか争いとなることがあります。
例えば、事業用の口座と個人用の口座を区別して利用していなかった場合、預金については全体が財産分与の対象となるということがあり得ます。
区別できるかどうかの判断は容易ではないので、専門家への相談がおすすめです。
会社名義の財産
会社と個人とは別の人格であるため、原則としては、会社名義の財産が財産分与の対象になることはありません。
もっとも、実体は夫婦共有財産であるが、形式的に名義のみ法人としていることが明らかなような場合には財産分与の対象となる可能性があります。
逆に、会社の利益圧縮のために夫ないしは妻に対して給料を支払い、その夫又は妻名義で貯蓄していた場合、財産分与の対象にはならない会社の財産であるとなる可能性は低いでしょう。
なお、会社に対する貸付債権は特段の事情のない限り財産分与の対象となります。
分与の割合
原則として、2分の1ルール(夫婦共有財産を半分ずつ分けるというルール)が適用されます。
例外的に、夫婦の一報の特別な才能や努力により資産形成がなされたと認められる事案では、寄与割合が修正される場合があります。
しかし、どのような場合に夫婦の一方の特別な努力や能力により資産形成がなされたといえるかは、個別具体的な事情によりますので、分与割合について主張がある場合は、一度専門家に相談に行ってみた方がいいでしょう。
夫婦の共有財産を特定するまでに時間がかかることが多いため、話し合いも長引きがちです。しかし、話し合いが長引いた場合、会社の経営への影響を無視できません。会社の運営に支障をきたさないためにも、トラブルが生じる前に一度弁護士に相談しておきましょう。